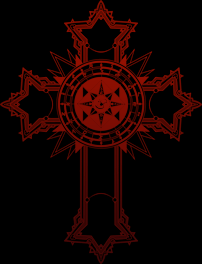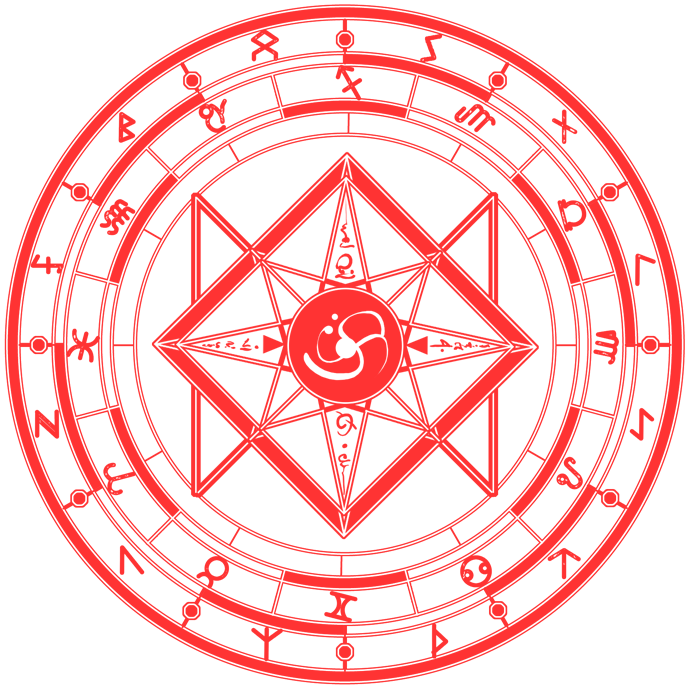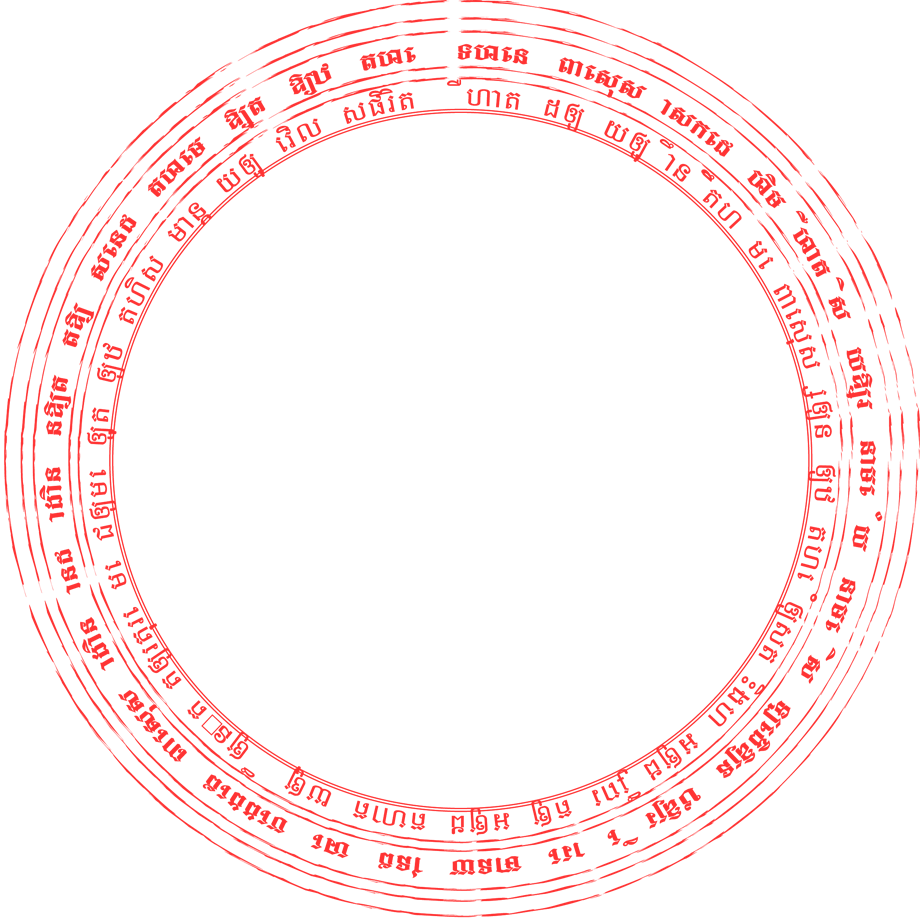1945年、5月1日……ドイツ。
陥落するベルリンにあって、ある儀式を行っている者たちがいた。
彼らにとって戦争に敗北することなど些事であり、むしろそれによって生じる夥しい犠牲者たちを、
儀式の触媒として生贄に捧げようとしていた。
その試みが成功したのか失敗したのか、誰にも分からない。
彼らは終戦後、行方をくらまし、生きているのか死んでいるのか、
そもそもそんな者たちが本当に存在したのか、やはり誰も分からないまま、噂だけが広がっていく。
聖槍十三騎士団――第三帝国の闇が生んだ超人たち。
彼らはいずれ戻ってくる。
そのとき世界は破滅する。
ゆえに、再来を許してはならない――と。
そして61年の歳月が流れた。
彼らを知っている者たちは、その大半が死んでしまい、皆が彼らを忘れていた。
しかし――
2006年……日本。
諏訪原市の学園に通う藤井蓮は、とある事件を境に親友・遊佐司狼と決裂し、
殺し合いじみた喧嘩の果てに二ヶ月間の入院生活を余儀なくされていた。
季節は秋から冬に――クリスマスを間近に控えた12月。
半身をもがれたような喪失感を覚えつつも、退院した蓮は司狼のいない新たな日常を構築し直そうと思っていた。
失ったものは戻らない。
ならせめて、今この手にあるものを大切にしたいと思いながら。
しかし、それすらも崩れ去る。
夜毎見る断頭台の夢。
人の首を狩る殺人犯。
それを追う黒衣の“騎士”たち。
常識を超えた不条理が街を覆い、侵食していく。
その異常は二ヶ月前の比ではなく、今まで積み上げてきたすべてのものを粉砕する暴力的なまでの非日常。
変わらなければ、生きられない。
生き残らないと、戻れない。
加速度的に狂っていく世界の中、蓮は独り、日常と非日常の境界線を踏み越える。
何も大層なことを望んでいるわけじゃない。
正義や大義を振りかざしたいわけでもない。
ただ、還りたいだけ。
つまらない、退屈だけど平凡で暖かかったあの頃に。
悲壮な決意を期する胸に、司狼の声が木霊する。
この街に住んでいたら、遅かれ早かれどいつもこいつも気が狂う――と。
聖槍十三騎士団との戦い。
狂気と殺戮と呪いに満ちた戦争の続き。
その果てに、蓮はいったい何を見るのか。